CSRDとは?
日本企業への影響やオムニバス法案による簡素化の動きを解説
- CSRD
- ESG経営
- サステナビリティ
- 情報開示
- サプライチェーン

公開日:2025年11月7日
企業サステナビリティ報告指令(CSRD)は、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する情報の開示を企業に義務付ける欧州連合(EU)の指令です。前身の非財務情報開示指令(NFRD)に代わり2023年1月に発効した同指令では、ESGに関する多岐にわたる開示が求められており、その一つとしてScope 3(スコープ 3)を含めたサプライチェーン全体における温室効果ガス(GHG)排出量などの開示が挙げられます。本記事ではCSRDの特徴や日本企業への影響、オムニバス法案による簡素化の動きについて解説します。
導入の背景や目的、NFRDとの違いは?
CSRDの前身であるNFRDでは、EU全体で非財務情報に関する拘束力のある基準がなく、法整備は各国の裁量に委ねられていました。具体的な報告内容が国や企業によって異なるため一貫性や信頼性を欠き、投資家のニーズに応えられないことが課題でした。
こうした背景から、サステナビリティに関する情報開示の強化を図るため導入されたのがCSRDです。これにより、報告内容が標準化され、一貫性・信頼性があり比較可能なESGデータを利用できるようになることが期待されています。
CSRDの特徴
CSRDは、企業にサステナビリティ情報の開示を義務付ける「法律(指令)」そのものです。そして、そのCSRDという法律のもとで、企業が具体的に「何を・どのように報告すべきか」を定めた詳細なルールが、ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)です。つまり、CSRDが「報告義務を課す」という制度の枠組みであり、ESRSが「報告方法を具体的に示す」基準という関係になります。
CSRDの主な特徴は、以下の通りです。
主な想定利用者
CSRDは投資家に限らず、広く一般の人々が比較可能で信頼できるサステナビリティ情報を利用できるようにすることを目指しています。CSRDの発効により、企業内外の様々なステークホルダーがサステナビリティに関する情報を比較し、より良い意思決定を行えるようになることが期待されています。
マテリアリティ(重要課題)の考え方
CSRDでは、「ダブル・マテリアリティ」の概念を採用しています。これは、サステナビリティに関する課題を、それが企業の財務状況や事業に与える影響(ファイナンシャル・マテリアリティ)と、企業活動が環境や社会に与える影響(インパクト・マテリアリティ)の両側から評価するものです。企業は、これらのいずれか、または両方の観点で重要と判断したサステナビリティ課題をマテリアリティとして特定し、ESRSに基づいた開示をすることが求められます。
サステナビリティ報告の基準は、CSRD/ESRSのような地域的な規制だけでなく、グローバルな統一基準を策定する動きも進んでいます。その中心的な役割を担っているのが国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)基準ですが、このISSB基準と整合性を図りながら、
日本企業の状況に合わせて開発されたのがサステナビリティ基準委員会(SSBJ)基準です。SSBJ基準とCSRD/ESRSを比較してみると、主な想定利用者やマテリアリティに対する考え方などにおいていくつかの違いが見られます。
しかし昨今、CSRD/ESRSとISSB基準との相互運用性を高める方針が示されるなど、国際的に基準を統一する動きが進んでおり、CSRD/ESRSに備えることはSSBJ基準への対応にもつながりそうです。
CSRD/ESRS、SSBJの比較
| 地域 | EU | 日本 |
| 主な法令・基準 | CSRD/ESRS | SSBJ基準 |
| 主な想定利用者 | すべてのステークホルダー | 投資家など |
| マテリアリティの考え方 | ダブル・マテリアリティ | シングル・マテリアリティ |
| 開示テーマ範囲 | サステナビリティ全般(10のテーマ別基準あり) | サステナビリティ全般(現在のところテーマ別基準は気候変動のみ) |
| GHG排出量の開示 | Scope 1、2、3 | Scope 1、2、3 |
| 適用時期 | 2024年1月〜段階的に適用 | 2027年3月期から順に義務化の見込み |
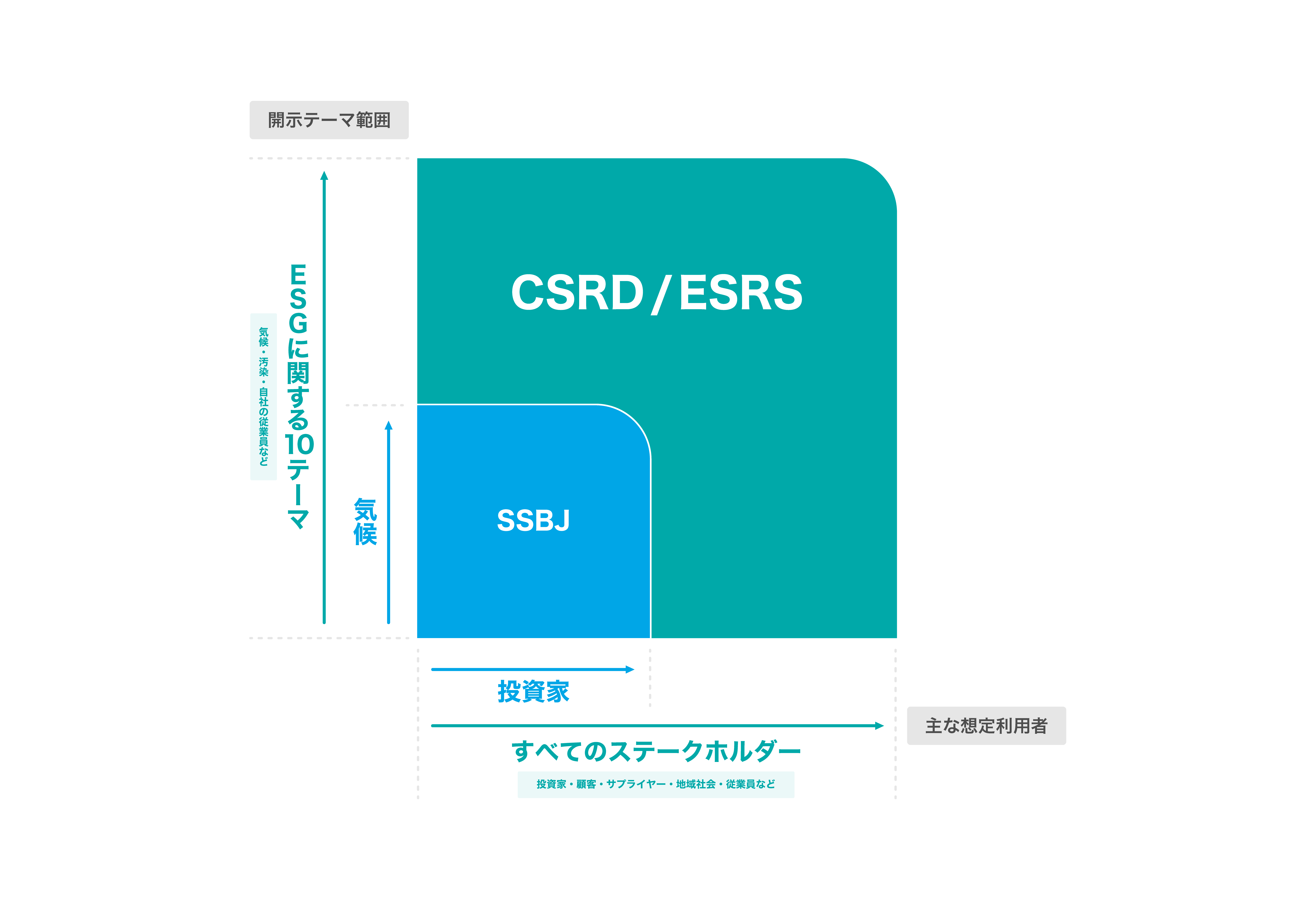
※今後の基準開発や後述の「オムニバス簡素化パッケージ」により変更の可能性があります
SSBJ基準に関する記事は こちら
とりわけ気候変動の領域では、CSRD/ESRSとSSBJ基準の両者においてサプライチェーン排出量の開示が義務化されます。これにより、自社によるGHGの直接排出(Scope 1)や、他社から供給されたエネルギーによる間接排出(Scope 2)に加え、原材料の調達や製品の輸送、使用、廃棄などScope 1、2以外の間接排出すべて(Scope 3)について開示が求められます。 このScope 3排出量を報告するためには、CSRDの適用対象企業が、自社のサプライヤーや物流委託先といった取引先から、それぞれの活動におけるGHG排出量のデータを提供してもらう必要があります。 つまり、CSRDの報告義務を負う企業から取引先に対し、排出量データ開示の要請がなされ、この動きがサプライチェーン上で連鎖していくため、CSRDの直接的な適用対象ではない企業にも影響が及ぶことになります。 結果として、多くの企業にとってサプライヤーの活動によるGHG排出量を算出・把握することが今後の課題となります。
日本企業への影響
CSRDはEU域内企業のみならず日本企業にも影響を与えます。EU域内に大企業に該当する子会社がある場合(以下の表 b)、または第三国企業(以下の表 d)に該当する場合は開示義務の対象となるため対応を検討する必要があります。
CSRDの適用対象
| 対象企業 | 対象企業の要件 |
| a.NFRD適用企業 | EU域内の従業員500名以上の上場企業など |
| b.大企業 | 以下のうち、2つ以上の要件を満たす企業 ・総資産2,500万ユーロ超 ・純売上高5,000万ユーロ超 ・従業員250名超 |
| c.中小企業 | 以下のうち、2つ以上の要件を満たす上場企業 ・総資産45万ユーロ超 ・純売上高90万ユーロ超 ・従業員10名超 |
| d.第三国企業 (EU域外企業) |
以下の要件を全て満たす企業 ・EU域内における純売上高が、直前の2会計年度連続して1億5,000万ユーロ超 ・EU域内に以下の子会社または支店を有する企業 子会社:大企業または上場企業 支店:純売上高が4,000万ユーロ超 |
規制を簡素化するオムニバス法案
詳細な開示により情報の透明性や信頼性が高まる一方、企業にとっては事務的な負担やコストが増大することが懸念されています。 こうした負担が企業の競争力を損ねかねないという指摘などを背景に、欧州委員会は2025年2月に規制簡素化を目的とした「オムニバス簡素化パッケージ(通称:オムニバス法案)」を発表しました。 パッケージには、CSRDを含むサステナビリティ報告義務の「延期に関する法案」と「開示項目の削減に関する法案」などが含まれています。
大企業・中小企業ともに開示開始時期は2年延期へ
同法案の一部として、まず開示開始時期の延期に関する指令が承認されました。NFRDの対象であるEU大手上場企業ではすでにCSRDの適用が始まっていますが、 2025年度に予定されていた大企業に対する開示の義務化は2年延期となり、2027年度から適用開始となるため該当する日本企業は注意が必要です。 また、中小企業においては、適用開始時期が2026年度から2028年度に延期されました。一方、直接日本企業が対象となり得る第三国企業への適応時期には変更がなく、2028年度から対応が求められます。
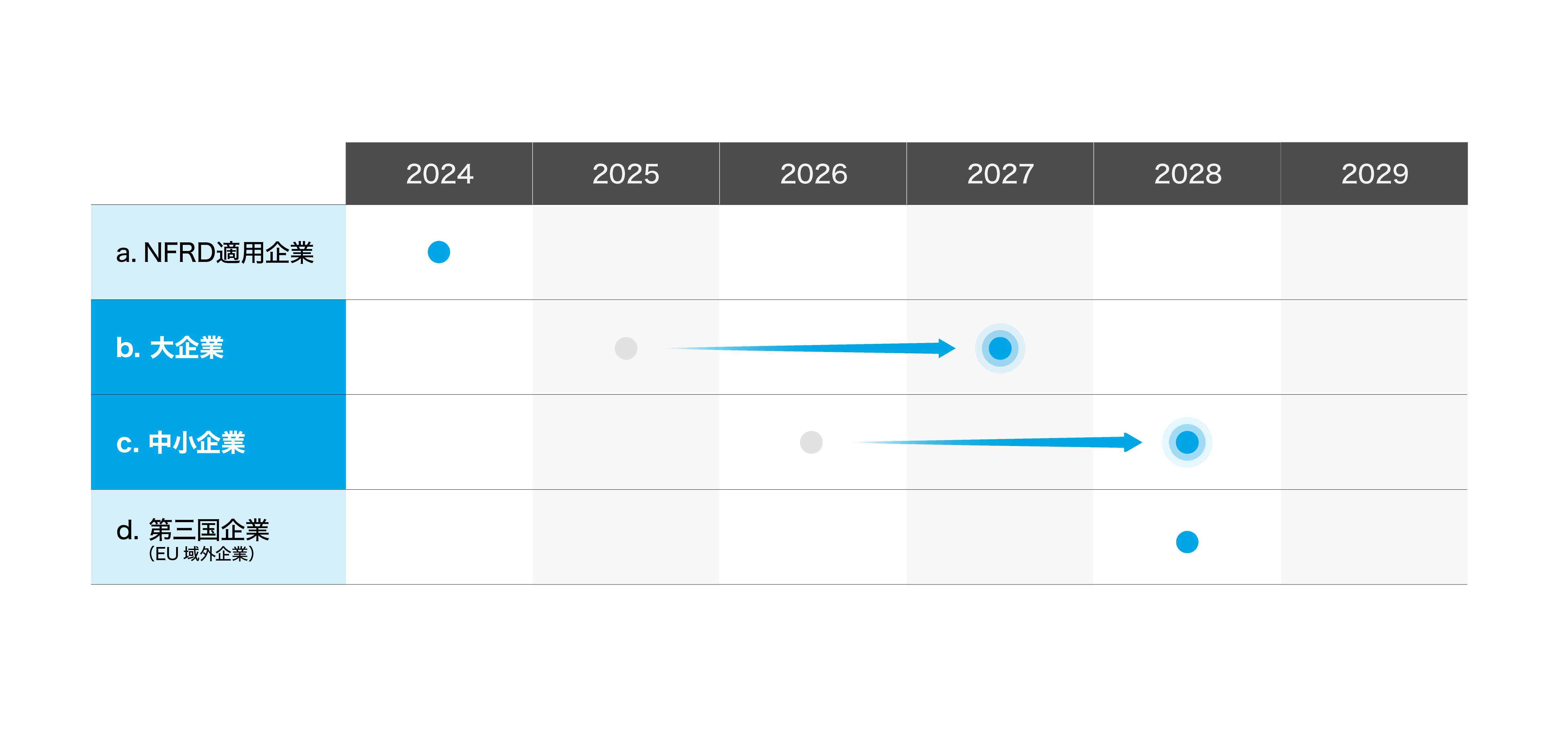
その他、適用対象の絞り込みなどに関しても審議が進められており、企業は今後の動向を注視する必要があります。
大負担軽減のため、開示項目5割以上削減の動きも開示項目を見直す動きも進んでおり、2025年6月には義務付けられていた1,000以上に及ぶデータポイントを5割以上削減する方針が示されました。 開示の負担を軽減するために注力するポイントとして、ダブル・マテリアリティ評価の簡素化や項目の整理が挙げられています。
効率的なデータ収集に向けて、SustainaLinkを
CSRDなどの開示規則は簡素化の動きがあるものの、サステナブルな社会の実現に向けて、企業による比較可能性と透明性のある情報開示が重要であることは変わらず、
サプライチェーン排出量の情報開示に関しては特に複雑なプロセスを伴います。企業の負荷を軽減しながら効率的にデータ収集を行うためにも、デジタル技術の活用は不可欠だといえます。
SustainaLinkでは、物流活動から排出されるGHG排出量の算定をサポートしています。CDPやSBTiなどからも推奨される業界ガイドライン「GLEC Framework」や国際規格「ISO14083:2023」が求めるプロセスに準拠しているため、
高品質な算定を行うことができるほか、国際輸送に関するGHG排出量の算定にも対応可能です。物流領域におけるGHG排出量の可視化をご検討の際は、ぜひ三井倉庫グループまでお問い合わせください。













