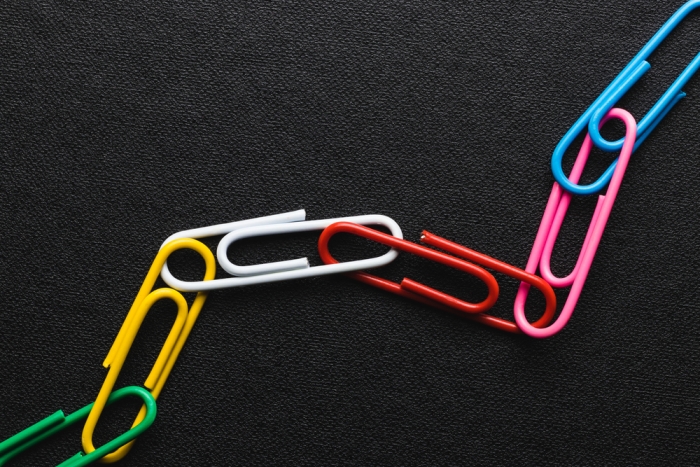(2023年12月8日最終更新)
人類の歴史において、物を「貯蔵する」、「運搬する」といった現在の物流の機能につながる行為は有史以前より営まれてきました。それらの行為は人々の生活や社会制度を支え、 そして発展させてきたという点で重要であり、人類が培った大切な知恵の一つといえるでしょう。
現在では、「保管(貯蔵)」を行う倉庫業者や、「輸送(運搬)」を行う運送業者などが物流業を営み、社会インフラとしての役割を果たしています。 こうした社会インフラとしての物流を構成する大事な要素の一つが「倉庫」です。物をある場所に留めておくこと、そして2地点間の移動の結節点としても利用される「倉庫」は、 物流において欠かすことのできない存在です。今回はこの「倉庫」に関する基礎知識を定義や歴史などを通じて紹介したいと思います。

倉庫とはなにか?定義・種類・機能について
倉庫の定義
はじめに、倉庫の定義について紹介します。
『[精選版] 日本国語大辞典』によると、「倉庫」は以下の通り定義されます。
①貨物の貯蔵、保管をするための建造物。蔵庫。
②倉庫営業者が、他人の物品を保管するために設けた建造物その他の設備。〔倉庫業法(1956)〕
次に、 倉庫業法による定義をみていきましょう。
倉庫業法第一章第二条では、
「この法律で『倉庫』とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作を施した土地若しくは水面であつて、物品の保管の用に供するものをいう。」と定められています。
これにより、「倉庫(物品を保管する施設)」には建物のほか、「工作を施した土地」や「水面」も含まれる、ということがわかります。
倉庫の種類
次に、商品などを保管する商業用倉庫の種類についてご紹介します。 商業用倉庫には、その管理主体によっていくつかの種類があり、製造業者や卸売業者が自らの物品を保管する「自家用倉庫」や、 倉庫業法による登録を受けた倉庫業者が他人から物品を預かり保管する「営業倉庫」などがあります。
この「営業倉庫」は倉庫業法で定められており、預かる物品の種類や管理方法などの違いによっていくつかの種類があります。
| 営業倉庫の種類 | 概要 | |
| 普通倉庫 | 1類倉庫 | 通常目にすることが多い、普通倉庫と呼ばれる建屋型営業倉庫の多くがこのタイプ。防水性能、防湿性能、遮熱性能、耐火・防火性能を備えたハイグレードな倉庫。 保管品は、日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械などの物品(第1類~第5類物品)。 |
|---|---|---|
| 2類倉庫 | 1類倉庫の要件のうち、耐火・防火性能を除いた倉庫。保管品は でん粉、塩、肥料、セメントなどの物品(第2類~第5類物品)。 | |
| 3類倉庫 | 1類倉庫の要件のうち、防水性能、遮熱性能、耐火・防火性能の他、防そ(鼠)措置を除いた倉庫。 保管品は、燃えにくく、湿気にも強い貨物であるガラス類、陶磁器、鉄材などの物品(第2類~第5類物品)。 | |
| 野積倉庫 | 屋外の、柵や塀で囲まれた区画にある倉庫。保管品は風雨や日光等による影響をほとんど受けない原材料(鉱物及び土石、原木等)、 れんが・かわら類など野積みの状態で保管することが可能な物品(第4類~第5類物品)。 | |
| 貯蔵槽倉庫 | 周壁により密閉されたタンク、サイロと呼ばれる倉庫。 保管品は、液体及び容器に入っていないばら穀物や、糖蜜などの液体物品(第6類物品並びに第1類~第2類物品のうち、ばらの物品)。 | |
| 危険品倉庫 | 消防法・高圧ガス保安法等が指定する危険物や高圧ガス(第7類物品)を保管する倉庫。 | |
| トランクルーム | 家財、美術骨董品、ピアノなど個人の財産を保管する倉庫。 | |
| 冷蔵倉庫 | 農畜水産物の生鮮品や冷凍品、加工品など10℃以下で保管することが適切な物品(第8類物品)を保管する倉庫。 | |
| 水面倉庫 | 原木等水面において保管することが可能な物品(第5類物品)を保管する水面上の倉庫。 | |
倉庫の主な機能
倉庫には単に物を「保管(貯蔵)する」機能に加え、以下のような機能があり、こういった観点からも人々の社会生活を支えていることが分かります。
- 重要物資の大量かつ安全な保管
- 輸送機関間の効率的な連絡調整
- 生産から消費までの時間差の調整
- 倉庫証券の発行による金融補助機能や商品受け渡しの簡素化
倉庫や倉庫業の誕生、そして近代的な倉庫について
次は倉庫や倉庫業の歴史について紹介いたします。
倉庫業とはなにか?
その前にまず、倉庫業について簡単に紹介いたします。
『倉庫論講義』(有田喜十郎 新東洋出版社)には、
「倉庫業とは、倉庫施設を経営し、用務を提供して貨物を保管し、荷役し、その報酬として倉庫料金(保管料、荷役料)を収得する事業である」とされています。
また倉庫業の役割について、国土交通省のウェブページでは以下のように記されています。
「倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。
他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。
登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。」[注1]
[注1]物流:倉庫業法|国土交通省
倉庫業は大きく分けると以下3つの種類があります。
- 普通倉庫業
農業、鉱業(金属、原油・天然ガス等)、製造業(食品、繊維、化学工業、紙・パルプ、機械等)といった幅広い産業の様々な貨物に加え、 消費者の財産(家財、美術品、骨董品等)も保管します。 法律上の分類による1類、2類、3類、野積、貯蔵槽、危険品倉庫を総称して、普通倉庫と呼んでいます。 - 冷蔵倉庫業
第8類物品(食肉、水産物、冷凍食品など10℃以下で保管することが適切な貨物)を保管します。 - 水面倉庫業
第5類物品(原木等)を水面で保管します。
倉庫と倉庫業の誕生
人類は原始の時代より、食糧や物品を倉庫に貯蔵してきました。エジプトの古都ルクソールで約3500年前のラムセス2世の時代に建造された倉庫群を現在でも見ることができます。 日本においては、弥生時代に農業が始まり、それに伴い穀物を貯蔵するための校倉造りの高床式倉庫がつくられるようになりました。 また、4世紀ごろからは天皇を中心とした統一国家が形成され、ヤマト政権の直轄領であり、稲穀を収納する官倉である「屯倉(みやけ)」が作られたとされています。 奈良時代には、国宝に指定されている正倉院が建てられました。聖武天皇の遺品の品、書物や宝、仏具など、古代の美術工芸や文化財が保管されており、 これらは時を超えて当時の日本を知ることができる貴重な史料です。倉庫には物のみならず、情報を保管する機能もあることが分かります。
中世に入ると、海上交易の発展に伴い商人の活動も活発になり、大量の商品を貯蔵するための倉庫もたくさん建てられるようになりました。 平安時代の末期においては河川の要港で貨物の保管・販売を行う「津屋」がうまれ、津屋が受け取る口銭「屋賃」が現在でいうところの「保管料」にあたり、これが倉庫業の起源であるといわれています。 「津屋」のビジネスからも分かるように、倉庫は「物流」だけでなく、「商流」や「金流」の結節点として機能してきたことがうかがえます。 鎌倉~室町時代の「問丸 (といまる)」、江戸時代の「問屋 (とんや)」 はその後身と言われています。
江戸時代には蔵屋敷が設けられ、諸藩に年貢米や土地の特産品を保管・販売する倉庫(住居も兼ねる)が建てられ、年貢米・特産品を現金化するための拠点として活用されました。 ここでの収入は幕府・諸藩の財政を支えました。
明治時代に入ると、廃藩置県などの大きな改革に伴い、国や藩ではなく民間の商人が大量の貨物を取り扱うようになりました。
蔵屋敷などの倉庫は民間に渡り、これが本格的な倉庫業の始まりだと言われています。
そのような中、三井倉庫ホールディンスの大元である「三井倉庫株式会社」も明治42年に「東神倉庫株式会社」として誕生いたしました。
ご興味のある方はぜひ沿革をご覧ください。

倉庫の近代化、高機能な倉庫へ
物流の主要な機能としては「輸配送 」や「保管」のほか、「梱包(包装) 」、「荷役 」、「流通加⼯ 」、「情報処理 」などがあり、
物流はサプライチェーンの中で重要な役割を果たしています。[注2][注3]
経済のグローバル化や顧客ニーズの多様化に合わせたサプライチェーンの高度化に伴い、物流のより一層の進化が求められるなか、倉庫の高機能化が進んでいます。
例えば、厳密な温度管理が求められるバイオ医薬品等を取り扱うことのできる定温倉庫や、地震や津波などの自然災害に備え、地盤の強い高台に建設され免震構造を有するBCP対応倉庫などが挙げられます。[注4]
[注2]物流とは何か?物流の起源や役割、そして課題について紹介!|三井倉庫グループ
[注3]サプライチェーンとは何か 具体例を交えて徹底解説|三井倉庫グループ
[注4]医薬品物流 ~医薬品・医療機器・治験薬の物流~|三井倉庫株式会社
人々の生活を支え、進化する倉庫
今回は「倉庫」に関する基本的な知識を、その定義や歴史などを通じて紹介しました。一見すると単に「物を保管しておくための施設」であり、地味に思われがちな倉庫ですが、 物流の要として社会の流れを支えていることをご理解いただけましたら幸甚です。 私たち三井倉庫グループは「社会を止めない。進化をつなぐ。」をPURPOSE(存在意義)として、倉庫業にかぎらず、総合的な物流業を営んでおります。何かお困りごとがありましたら、何なりとお問合せください!
【参考】
- 加藤書久(2002)『倉庫業のABC』 成山堂書店
- 有田喜十郎(1972)『倉庫論講義』 新東洋出版社
- [精選版] 日本国語大辞典 小学館
- 物流:倉庫業法|国土交通省
- 倉庫業について|一般社団法人 日本倉庫協会
- 第19号倉庫の歴史と今後必要とされる方向性について|サカタウエアハウス株式会社
- 倉庫の歴史を知る|スクロジマーケティング株式会社
- 倉庫の歴史|株式会社山清倉庫
- 営業倉庫とは?営業倉庫の種類と自家用倉庫との違いについて解説|株式会社APT