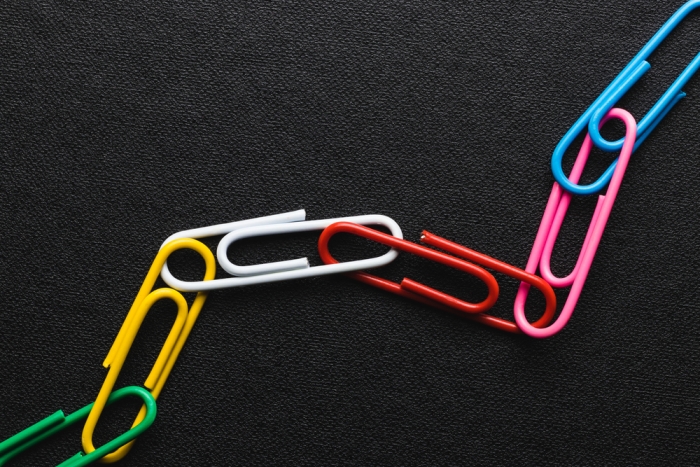わが国の経済・社会生活を語るうえで、諸外国との貿易取引の存在を外すことはできません。昨今では新型コロナウイルス感染症拡大等の影響もあり、貿易取引の額自体は減少してるものの、自動車や半導体など日本で作られた製品の輸出や、食料やエネルギー資源の輸入を通じて、私たちの経済や社会が支えられていることは言うまでもありません。
こうした貿易取引の迅速化や効率化に大きく貢献しているのがNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)です。NACCSは、輸出入、港湾・空港手続及び貨物管理等民間業務を処理する官民共用システムで、貿易取引に関わる多くの関係者がNACCSを通じて輸出入申告をはじめとする税関手続き等を行っています。 今回はこのNACCSについて解説していきます。

NACCSとは何か
NACCSとは「入出港する船舶・航空機及び輸出入される貨物について、税関その他の関係行政機関に対する手続及び関連する民間業務をオンラインで処理するシステム」で、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社が管理・運営等を行っています。[注1]
海外との商取引である貿易活動の中で、NACCSは以下に挙げる様々な行政手続きを電子的に処理しています。
| 主な行政手続き | 関係省庁 |
|---|---|
| 税関手続 | 財務省・税関 |
| 港湾手続 | 国土交通省等 |
| 乗員上陸許可手続 | 法務省 |
| 貿易管理 | 経済産業省 |
| 動植物検疫手続 | 農林水産省 |
| 輸出証明書等手続 | 農林水産省等 |
| 検疫手続 | 厚生労働省 |
| 食品衛生手続 | |
| 医薬品医療機器等手続 |
[注1]NACCSパンフレット|輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
また、こうした行政手続きをNACCS上で行う利用者としては以下が挙げられます。[注2]
| 主な利用者 | 代表的な業務 |
|---|---|
| 輸出入者 |
|
| 通関業 |
|
| 海貨業 |
|
| 船会社、船舶代理店 |
|
| 航空会社 |
|
| 損害保険会社 |
|
NACCSの歴史
現在のNACCSは海上貨物と航空貨物の両方の行政手続きや関連する民間手続きを処理することができますが、稼働開始当時は海上貨物と航空貨物のそれぞれの手続きを行うシステムとして分かれていました。
まず、航空貨物の輸入手続きを行うシステムとして登場したのがAir-NACCSです。Air-NACCSは1978年より稼働し、その後1985年には輸出手続きも行うことができるようになりました。また、海上貨物の輸出入通関システムとして登場したのがSea-NACCSです。Sea-NACCSは1991年より稼働しています。
そしてこれら海上貨物・航空貨物それぞれのNACCSに加え、関係省庁のシステムが統合され、2010年に第5次NACCSが誕生しました。その後、様々な機能追加が行われ、2017年には現行の第6次NACCSに移行しています。第5次NACCSから第6次NACCSへの移行の際には、「グローバルサプライチェーンの進展」や「我が国産業・港湾の競争力の維持・強化」、「ユビキタス社会の進展」など、社会環境の変化に対応して以下をその開発コンセプトとしていました。
- 官民共同利用の基幹システムとして、安定性・信頼性の高いシステムの実現
- 公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステムの実現
- 総合的物流プラットフォームとしての更なる機能の充実

第7次NACCSについて
2017年より稼働している第6次NACCSはそのシステムライフを8年としていることから、2025年には第7次NACCSへとシステム更改が行われる予定です。第7次NACCSの開発コンセプトとしては、第6次NACCSの3つの開発コンセプトをベースに、最新技術や各種デジタルプラットフォームとの連携を見据え、「国際物流に関連した最新技術の応用・周辺の貿易情報基盤との連携の可能性」というコンセプトを加え、以下4つをその開発コンセプトとしています。[注3]
| 開発コンセプト | 概要 |
|---|---|
| 官民共同利用システムとして、安定性・信頼性の高いシステム |
|
| 公共的インフラとして、効率性・経済性の高いシステム |
|
| 総合物流情報プラットフォームとしての更なる機能の充実 |
|
| 国際物流に関連した最新技術の応用・周辺の貿易情報基盤との連携の可能性 |
|
最新技術としてはAIの活用に加えて、クラウドサービスやAPI公開等の検討が行われており、入力補助機能の導入によるUIの改善、開発工数の短縮や運用・管理業務の軽減などの効果が見込まれています。
[注3]第7次NACCS基本仕様書|輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
また、デジタルプラットフォーム連携においては以下が検討されています。[注4]
| 主なプロジェクト | 概要 |
|---|---|
| 港湾関連データ連携基盤 | 港湾関連データを集約し、主に民民間の電子的情報の共有を目指す。 |
| 貿易手続データ連携システム | ブロックチェーン技術を活用し、貨物や輸出手続きに関するデータを管理・共有することで、手続き業務に関わる事業者の生産性向上と輸出リードタイム短縮を目指す。 |
|
貿易情報連携基盤 (TradeWaltz) |
ブロックチェーン技術を活用した情報連携基盤を構築し、金融分野まで含めた貿易手続きの効率化、迅速化、利便性の向上を目指す。 |
| TradeLens | ブロックチェーン技術を活用したデジタルオープンプラットフォームによりコンテナ貨物等のステータス情報を関係者間で共有。諸外国のターミナルや港湾、船会社、税関等が参加している。 |
|
GSBN (Global Shipping Business Network) |
複数の大手船社やターミナルオペレーターが参加し、他のプラットフォームとの接続・連携を打ち出すことで業界標準を目指す。 |
[注4]第7次NACCS基本仕様の概要(第5回)|輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

我が国の経済・社会生活を支えるNACCS
これまで見てきたとおりNACCSの稼働開始以来、さまざまな国際物流に関する手続きが迅速かつ的確に処理できるようになったことに加え、外部環境の変化にともなって、新しい機能の追加、さらにはシステムの対応範囲の拡大などが行われてきました。国際物流におけるインフラであるNACCSは、貿易大国日本の経済や社会を支える存在といえるでしょう。
※当コラムで記述されている内容は全て掲載当時のものです。最新の情報につきましては都度ご確認いただくことをお勧めいたします。